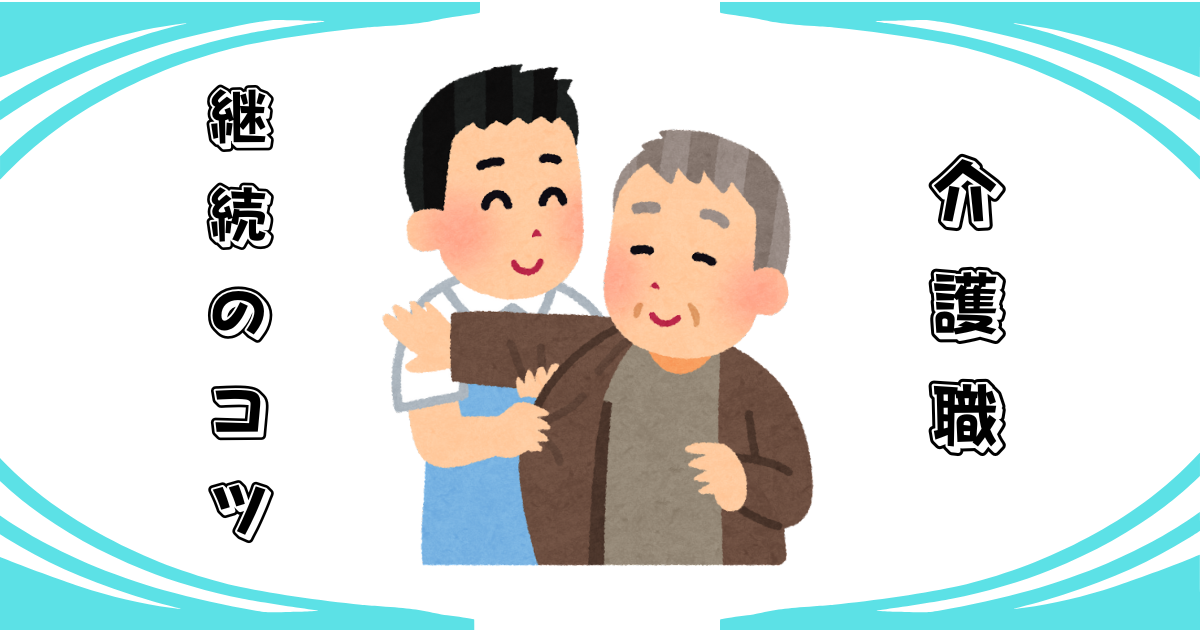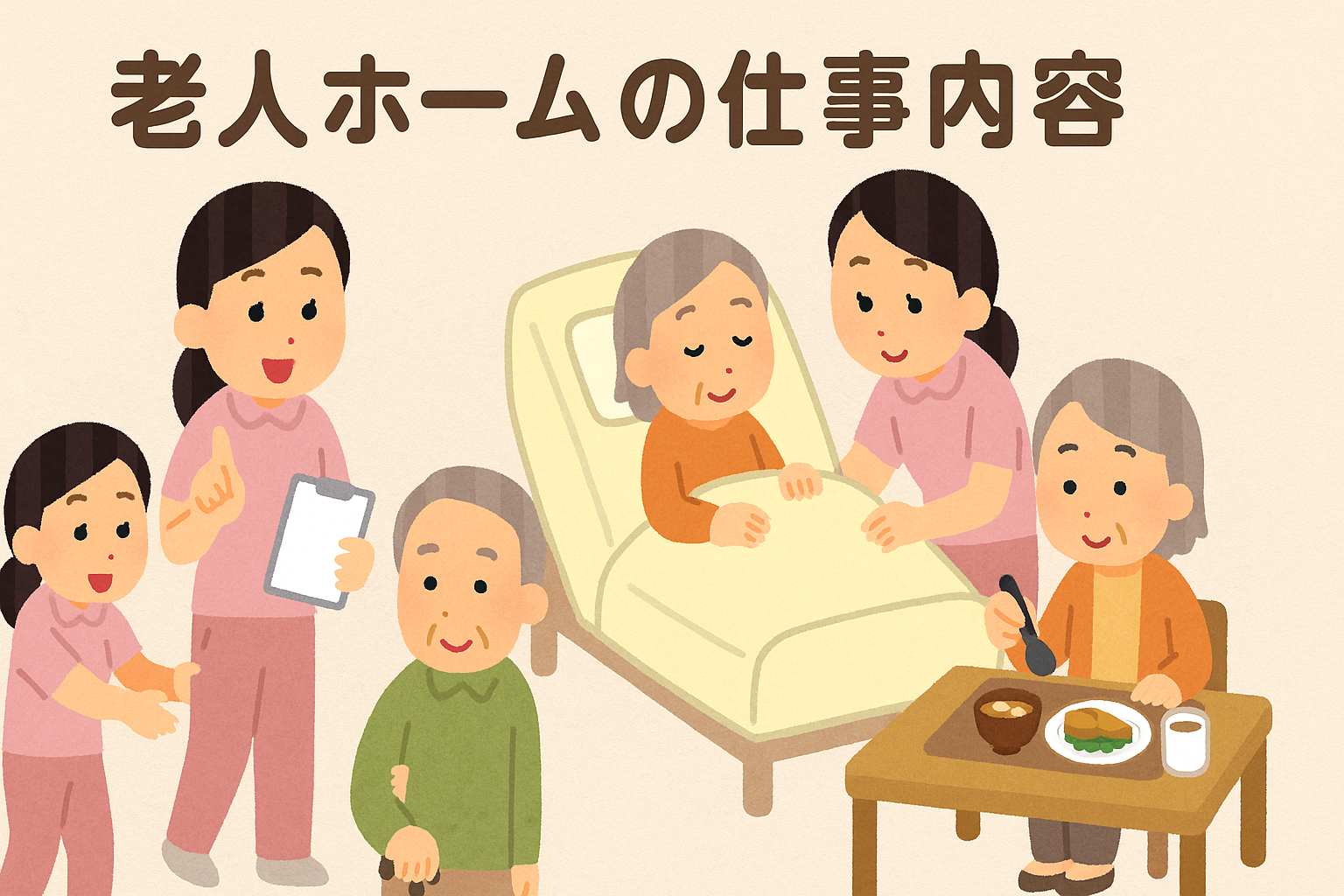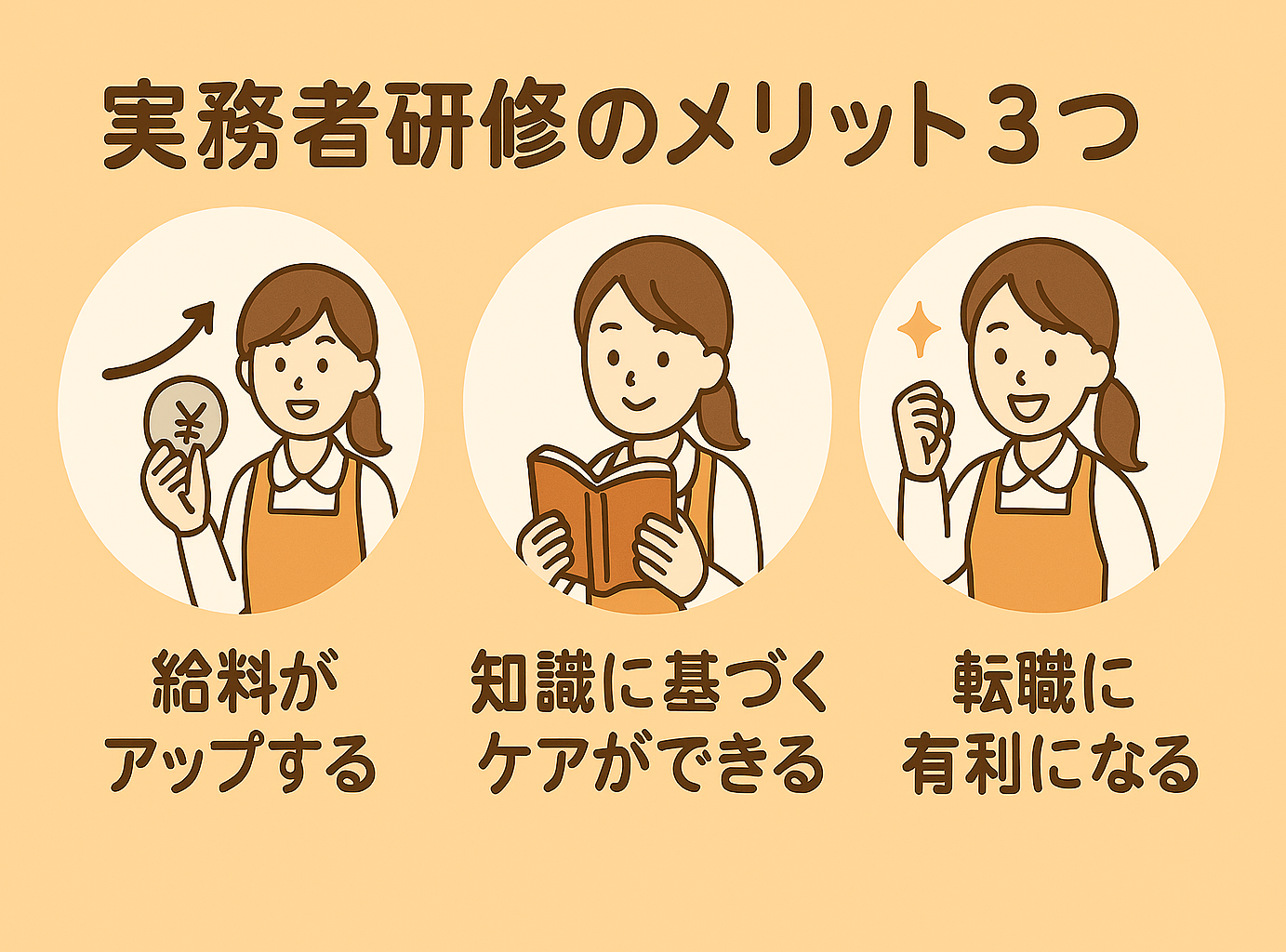介護の仕事に転職すると、またゼロから新しい職種で経験を積むことになります。他の職種に比べて年齢層が高めな職場も多く、落ち着いた雰囲気で馴染みやすいと感じるかもしれません。
私が住宅型有料老人ホームで訪問介護の仕事を始めたときは、わずか4日で独り立ちとなりました。初任者研修は修了していたものの、現場での実務は初めて。排泄介助の方法や準備の手順など、一つひとつ丁寧に教えてもらえたのはありがたかったです。
わからないことは自分で調べたり、先輩に積極的に聞くようにしていたところ、「やる気のある新人」と受け入れてもらえることが多く、人間関係にも恵まれました。
とはいえ、仕事をしているうちに「このやり方で本当にいいのかな?」と疑問がわいたり、利用者さんとの関係に悩んだりすることもあり、モチベーションが落ちる時期もありました。
今回は、そんなときにどうやって気持ちを切り替え、仕事を続けられたか、私なりのコツを3つに分けてお伝えします。
① 人間関係は「3対4対3の法則」で乗り切る
介護職は「人と関わる」仕事です。職員同士だけでなく、利用者さんとの関係も大切。その分、どうしても人間関係の悩みは避けられません。
以前、介護専門の転職エージェントの方から「転職理由の75%は人間関係」と聞いたことがあります。たしかに、どれだけ誠実に接していても、相手に合わなかったり、時には敵意を向けられることもあるんですよね。
そんなときに私が参考にしているのが、「3対4対3の法則」です。
これは、「どんなに頑張っても、自分のことを好意的に見てくれる人は全体の3割。中立的な人が4割。残りの3割は、何をしても合わない人」という考え方です。
この考え方を知ってからは、「なんか合わないな…」と感じる相手には、無理に好かれようとせず、最低限の挨拶や報告連絡だけにとどめるようにしました。
逆に、自分に好意的だったり、中立的な人とだけでも良好な関係を築けていれば、それで十分。無理せず自分の心を守ることも、長く働くためには大切です。
② 疲れを溜めない工夫と、家事との両立
介護の仕事は、体力勝負です。腰痛をはじめ、立ち仕事による足の痛み(足底筋膜炎など)に悩まされることもあります。
体に負担をかけない「ボディメカニクス」という介護技術もありますが、すぐに身につけられるものではありません。現場での経験を通して、少しずつ自分の動きに取り入れていくことが大切だと感じました。
疲労回復には、睡眠や食事などの自己管理も重要です。
また、働いた後に待っている「家事」との両立も一つの壁です。労働時間が長くなるほど、家事が重荷に感じることも。
そんなときは、
- 家族に協力してもらう
- 自動調理器やロボット掃除機など、家電の力を借りる
- ルーティンを決めて迷わないようにする
など、日常をシンプルにする工夫で負担を軽くすることができました。
③ 継続のコツは「ゴール設定」
どんな仕事でも、先が見えないとつらくなってしまうものです。
私は「まず3年働いて介護福祉士を目指す」という明確な目標を立てました。介護福祉士になるには、実務経験に加えて「実務者研修」の修了が必要です。この研修を受けることで、サービス提供責任者などのステップアップも可能になります。
つらいときほど、「〇年後には資格が取れる」「この契約が終わったら次のステージへ」といった期間限定の目標を意識すると、「あともう少し頑張ってみよう」と前向きに考えられるようになります。
実際、気がつけばスキルも身につき、自信が持てるようになったり、より良い条件での転職につながることもあります。
最後に
介護の仕事はやりがいがある反面、心身ともにハードな面もあります。それでも、自分に合ったやり方で「どうしたら続けられるか?」を工夫していけば、少しずつ道が開けていくと実感しています。
もし今、モチベーションが下がっている方がいたら、「人間関係の法則」「体をいたわる工夫」「小さなゴール設定」、どれかひとつでも試してみてくださいね。