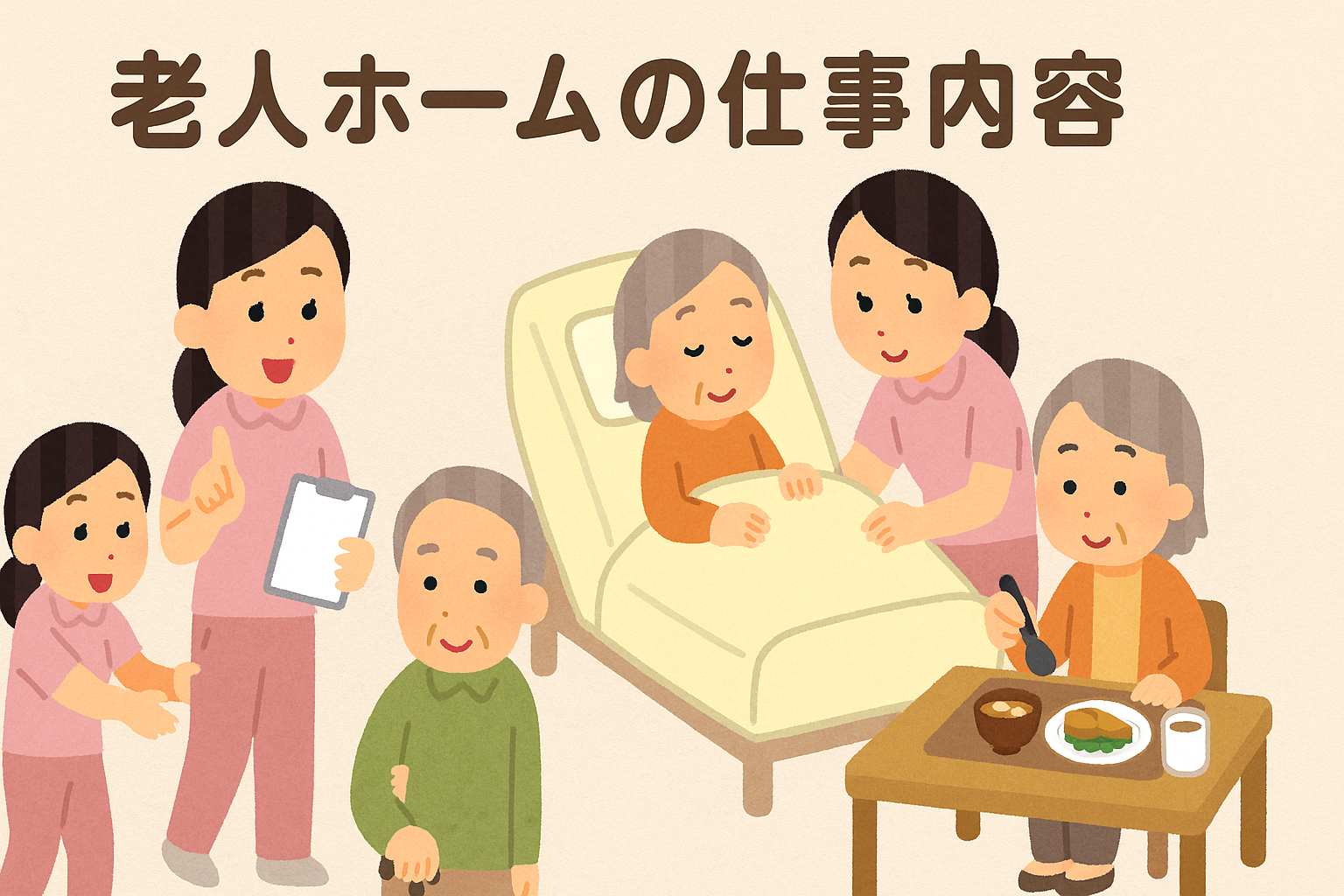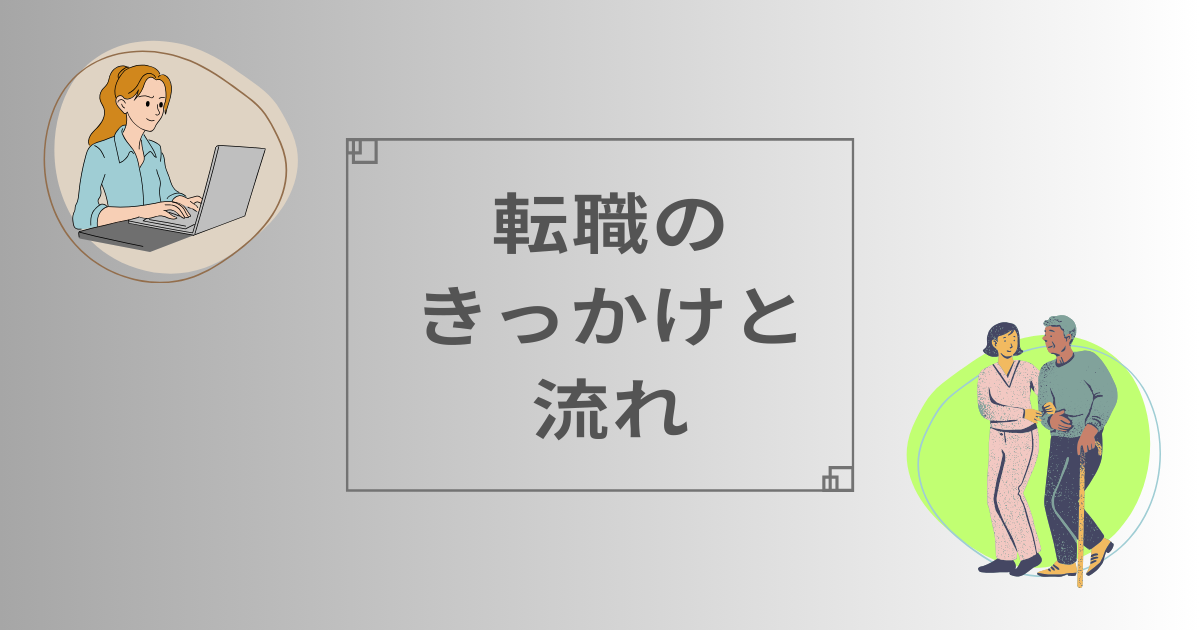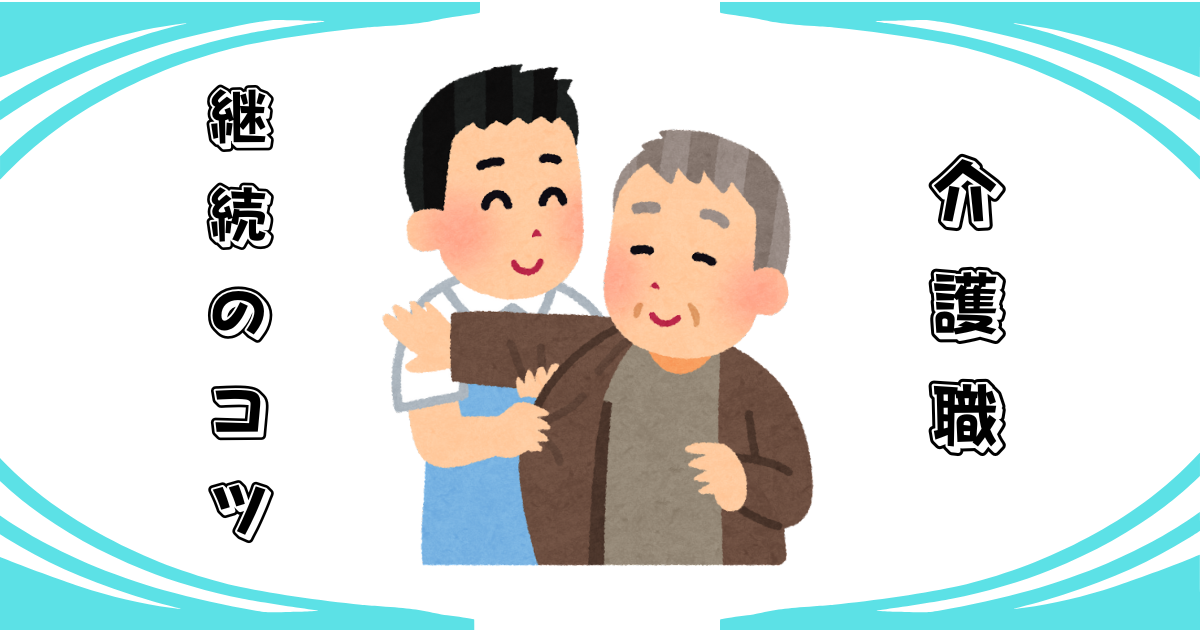老人ホームは、利用者の生活の場。24時間365日、施設は休むことなく稼働しています。今回は、私が以前勤務していた「住宅型有料老人ホーム」での日勤帯の仕事内容や、施設全体の動きについてご紹介します。
住宅型有料老人ホームの特徴
私が働いていた施設には、各フロアに24〜26の個室があり、利用者の皆さんは、ベッドやテレビ、整理タンスなどを持ち込んで、自分の部屋として生活していました。
住宅型の施設では、訪問介護形式でケアを行います。ケアプランに基づき、職員が利用者の居室を訪問し、入浴や掃除、排泄などの日常生活支援を提供します。
私が担当していた日中の主な業務
日勤帯の時間に私が行っていた仕事は、主に次のような内容です。
① 入浴介助
居室でバイタルチェックと体調確認を行い、着替えの準備を手伝います。その後、浴室に案内し、入浴の介助を行います。
② 居室清掃
掃除機がけや拭き掃除、ベッドのシーツ交換、布団・枕カバーの取り替えなどを行います。
③ 買い物代行
コロナ禍だった当時は、買い物も代行が中心でした。利用者から必要な日用品の銘柄を聞き取り、職員が代わりに買い出しに行っていました。
④ 排泄介助
トイレへの誘導や、オムツ・リハビリパンツの交換を行います。
出勤後は、その日の担当利用者やケア内容が書かれたプラン表を確認して、業務に入ります。多くの日は、①~④の業務がバランスよく組み込まれていました。
日勤帯職員の1日の流れ
以下は、日勤シフトの大まかなスケジュールです。
- 9:00~12:00 入浴・清掃・買い物・排泄介助などケアプランに沿った支援
- 12:00~13:00 昼食介助・服薬サポート
- 13:00~17:00 引き続きケア業務やレクリエーション
- 17:00~18:00 夕食介助・服薬サポート
また、他のシフトの職員たちは次のように動いています。
- 早番職員(7:00~16:00)
起床時の更衣介助、朝食や服薬介助などを担当 - 遅番職員(11:00~20:00)
夕方から就寝前までの対応を担当 - 夜勤職員(16:00~翌10:00)
夕方から朝までの安否確認、コール対応、夜間の排泄介助などを行う
コロナ禍ならではの業務の大変さ
当時は、デイサービスの利用が控えられていたため、入浴や排泄介助の回数も増加。その上、感染症対策や罹患時の対応にも細心の注意が必要で、普段のケアに加えて神経を使う場面が多く、大変だった記憶があります。
チームで支えるケア体制
介護職員のほか、身体介護(入浴・排泄)を行わない生活援助ヘルパーも、各フロアに1人ずつ配置されていました。彼らは主に、食事の準備や片付け、廊下や共有部分の清掃などを担当していました。
生活援助からスタートし、初任者研修を受けて介護職員になるという流れの方もいて、さまざまな勤務形態(パート・正職員)や時間帯に合わせた働き方ができるのも、この施設の特徴でした。
最後に
送迎業務がなく、日々のケアが個別に行われる住宅型の有料老人ホームは、未経験からでも始めやすく、介護の仕事に慣れていくには適した環境だと感じました。これから介護職を目指す方の参考になれば嬉しいです。